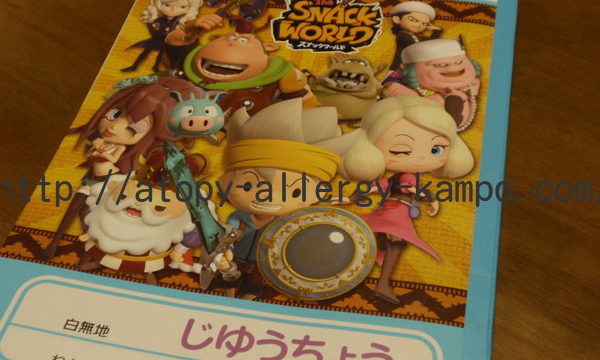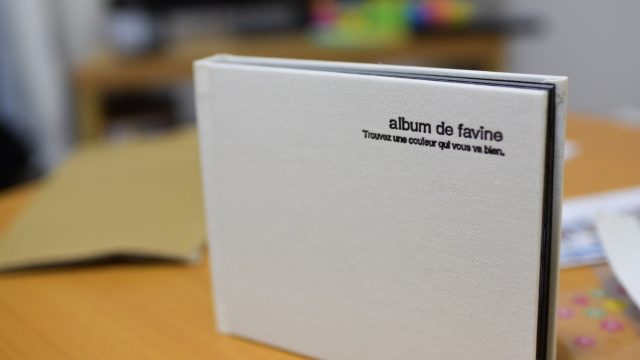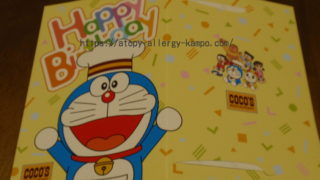今回は小1息子も持つランドセルの話題です。
ランドセルって確かに重いですよね。
さらに、最近ではほぼ毎日持って行くこくごやさんすうの冊数が多いこと(驚)
教科書だけでなくドリルや練習帳などを合わせると、こくごだけで5~6冊になります。
さんすうも4冊くらいと計算カード、他の教科(音楽や図工など)があるとさらにランドセルは重くなります。
1年生でこれですから、これからどうなるのやら・・と思ってしまいますね。
1年生も後半戦で随分ランドセルを持つことや通学にも慣れてきましたけれど、やっぱり重い。
ちょっと前に道徳と生活の教科書は、学校預かりになりましたけど。
私の滋賀に住む友人は、子供が小学生の頃は『ランリュック』を背負って登校していたと以前話していました。
その時は『へ~そうなんや』程度でしたが、最近この『ランリュック』正式には『ランリック』についてのニュースを見ました。
ちょっと紹介しつつ、私の感想も書いてみますね。
読みたい場所へジャンプ
■「ランリック」とは?

出典:ランリックホームページより
http://ranrick.com/
『ランリック』のニュースはコレです。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181127-00028455-otonans-soci
ただヤフーニュースってそのうち削除されることもあるので、文章だけ以下に書き写しますね。
ネットで読めた人は、ジャンプしてもらって大丈夫です。
ジャンプする人は↓↓ジャンプ~を押してくださいね。
ジャンプ~
記事はここからです。
小学生の重すぎるランドセル問題に一石? 京都などで使われる軽量の「ランリック」とは 11/27(火) 11:21配信 オトナンサー
「重すぎるランドセル」が小学生の負担になっていると指摘されています。
文部科学省は、教材の一部を学校に置いて帰る「置き勉」を認めるよう、各教育委員会に通知していますが、「通学かばん自体を軽い物にする」という選択肢はないのでしょうか。
小学生の通学かばんはランドセルが主流ですが、一部地域では、リュックサックタイプのかばんなど、ランドセル以外のかばんが使われています。
いじめの相談から誕生した
ランドセルメーカーの業界団体「ランドセル工業会」がホームページで公開している「ランドセル130年史」によると1887(明治20)年、皇太子時代の大正天皇に、当時首相だった伊藤博文が、学習院小学校の入学祝いとして箱型の通学かばんを献上したのがランドセルの始まりとされています。
背中に背負うことができ、両手を自由に使えるランドセルは全国的に普及。
一時、重さや価格の高さから、ランドセル通学を廃止する地域があったものの、業界側から教育委員会へ働きかけるなどして、多くの地域で「小学校の通学かばんはランドセル」という認識が定着したとのことです。
そうした中、京都府南部の小学校などでは、「ランリック」というリュックタイプの通学かばんが使われています。
製造している「マルヤス」(京都府向日市)広報担当の鈴木康弘さんに聞きました。
Q.ランリックは、いつから販売しているのですか。
鈴木さん「今からちょうど50年前、1968年に誕生しました。
当時のランドセルは今よりも重く高価で、保護者の負担も子どもたちの負担も重いものでした。
そんな中、京都府長岡町(現・長岡京市)の長岡第三小学校の校長先生(当時)から、ランドセルに代わる通学かばんの製造を依頼されました」
Q.詳しく聞かせてください。
鈴木さん「高価なランドセルを買えない保護者が、豚革のランドセルを子どもに買い与えました。
その子は喜んでいましたが、学校では『これはブタや、ブタ、ブタ』といじめられ、学校へ行くのが嫌になったというのです。
校長からその話を聞いた私の祖父・鈴木正造が、安くて遠足にも使える、お金があまりかからないものを、とリュックタイプのかばんを作りました」
Q.商品名は「リュック」ではなく「リック」ですね。
鈴木さん「リュックサックのことを、祖父は『リックサック』と言っていて、『ランドセル』の『ラン』と合わせて商品名になりました。
実際には『ランリュック』と呼んでいる人が多いようです」
Q.現在、どの程度の地域、学校で使用されていますか。
鈴木さん「約200校です。京都府の南部地域を中心に、滋賀県、大阪府、埼玉県、山口県、新潟県、福岡県などで使われています」
Q.価格はどのくらいですか。
鈴木さん「オンラインショップで税込み8856円~1万2312円です。
ランドセルは安いものでも3万5000円くらいですから、かなり安いと思います」
Q.ランドセルの重さは1.2~1.4キロが平均的なようですが、ランリックの重さを教えてください。
鈴木さん「重さは670グラムから760グラムです。
材質はナイロンです。
軽くて、耐久性がある素材を、と選びました」
Q.ランドセルは6年間使い続けられることがメリットと言われますが、ランリックは何年間くらいの使用を想定していますか。
鈴木さん「女の子は6年間大丈夫です。
男の子は放り投げたり、蹴ったりする子もいるので、ちょっと厳しいところもありますが、多くの皆さんが6年間、使われます。
ランドセルとそん色ないと思います」
Q.ランリックをランドセルと比べた場合のメリット、デメリットを教えてください。
鈴木さん「メリットは安さと軽さです。
メインの商品は、黄色と黒という交通安全標識によく使われる色で、よく目立つのも特徴です。
子どもたちの交通安全のことを考えた色です。
デメリットとしては、水に弱いことです。
生地に撥水加工はしているのですが、大粒の雨には弱いので専用のカバーも売っています。
また、革のランドセルに比べると見劣りする面はあり、ランドセルを使っている地域から引っ越してきた人は、最初は抵抗感があるようです」
Q.ランリックなどリュックタイプのかばんにもメリットがあるのに、日本全体としてはまだまだランドセルが主流なのはなぜでしょうか。
鈴木さん「昔から『小学生といえばランドセル』というイメージがあるからではないでしょうか。
入学時、おじいちゃんやおばあちゃんが贈るものであり、贈るのであれば高級なものを、という慣習が続いているのかもしれません。
さらに、ランリックなどの代替品があることを知らない人も多いと思います。
また、『ランドセルでないといけない』という固定観念もあると思います」
念のため、文部科学省に確認しましたが、「小学校の通学かばんに決まりはありません」とのことでした。
記事はココまで
■『ランリック』いいですねぇ~!軽い方がイイし安い方が助かる(^^)
前述滋賀の友人からランリックの話を聞いたとき、友人はやっぱりランドセルを持たせたいけど・・と話していました。
小学生と言えばランドセルのイメージが強いですし、確かに見た目もランドセルの方がいい気がします。
けど、最近は教科書も学習する内容が増えるにしたがって重くなりますから、せめてカバンは軽い方がいいですよね。
お値段も安いですし、私もランリック賛成です。
ただこういうのって地域単位ですから、変えるのもなかなか大変そうですけどね。
ランリックが多くなると、ランドセルメーカーが困るかもですが・・
学校に教科書を置く置き勉を認めてもいいと思うのですが、この教科書が今日の勉強に必要か否かはさすがに小学校低学年では判断できません。
持って行ったものを持って帰る、もしくは一切持って帰らないしか混乱しそうです。
けど、一切持って帰らないのなら普段はランドセルが空くってことですから、ランドセル自体要るの?って思ってしまいます。
あ!宿題だけ持って帰るってことですかね。
けど教科書って家でパラパラ見たり、次は何の勉強をするのかを確認したり、また復習するのにも使いますしね。
機能性を考えるとランリックですねぇ、やっぱり。
どう思いますか?
ご意見ご感想などがあれば、コメントを残してくださいね(^^)